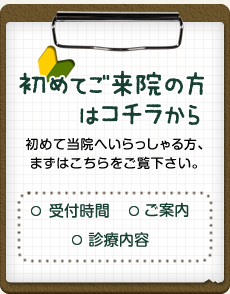ペットの病気について
猫にもフィラリア予防を
犬を飼っている方は蚊によって媒介されるフィラリア症という病気をご存知かと思います。
フィラリアといえば犬だけに感染する病気だと思っている飼い主さんは意外と多いのではないでしょうか。もちろんフィラリアが成長するのに最も適した環境は犬の体内であり、別名「犬糸状虫」という和名からも犬だけに感染する病気と誤解を与えやすいのですが、フィラリアは猫にも感染する病気なのです。
猫のフィラリア症は犬と同様、猫の肺動脈に寄生します。犬と猫の違いは、成虫の生存期間が猫は2~4年と短い点(犬は5~6年)、成虫が雌雄どちらか一方だけなので繁殖できない点(犬は繁殖可能)、そして数がせいぜい1~3匹とかなり少ない点です。
感染する確率も犬より低いです。しかし猫の心臓は犬の心臓よりはるかに小さいため、ひとたびフィラリアに感染すると、たとえ虫の数が少なくても重症化する傾向にあります。
症状としては咳、呼吸困難、食欲不振、元気消失などがあり、突然死する場合もあります。他の病気と区別しにくいのが特徴で、気が付いた時には手遅れというケースも多いようです。
犬の場合は顕微鏡でのミクロフィラリア検査、検査キットを使った抗原検査でフィラリアの感染を調べることができますが、猫にはこれらの検査はあまり有効ではなく感染を調べるのは犬よりも非常に難しいです。
フィラリアに感染しないためには、予防薬で予防をしていただくことが何より大事です。

予防薬といっても犬用のものではなく、猫にも専用の予防薬があります。犬と同様、決められた期間毎月予防薬を投与することでフィラリアの感染を防ぎます。
犬と比較してみると発生率も認知度も低い猫のフィラリア症ですが、ここ最近では注目されてきており、動物病院でも猫への予防もすすめるようになってきています。
蚊が多く発生している地域に住んでいる場合や外にも出て行ってしまう猫を飼っている場合は蚊に刺される率が高くなるので予防していただくことをおすすめします。
デリケートな犬猫の皮膚について
犬猫の皮膚は人と比べて半分以下の厚さで、とても薄くデリケートなのをご存知ですか?
犬や猫はたくさんの毛で被われており、毛で隠れた皮膚の状態まで普段あまり目がいかないものだと思います。
強くこするなど、物理的な刺激には非常に弱いのです。皮膚が薄い分、犬猫では豊富な被毛に覆われています。
人の毛穴から出ている毛は1本~数本ですが、犬猫の毛穴からは多いと数十本以上の毛が伸び出しています。また、人の皮膚のpHは弱酸性なのに対して、犬や猫は弱アルカリ性の皮膚を持っています。犬猫用シャンプーは犬猫の皮膚のpHに合わせてつくられているのです。
犬猫が人と同じように汗をかくのはイメージしにくいのではないでしょうか?実は犬猫も汗をかきます。ただ、汗の質が人とは違っていて、毛穴からべたつきのある汗がジワジワと出ています。
とてもデリケートな犬猫の皮膚ですが、たくさんの毛で保護されているため、ある程度の健康は保たれています。けれども、何もケアをせずほったらかしにしていたら、いつトラブルが起こってもおかしくありません。
まず直接目でみて手で触れて、皮膚に異常がないか確かめましょう。
皮膚に関するトラブルは犬猫に多い病気で、症状も原因も様々です。
痒みを伴う皮膚トラブルにはアレルギー性のものや細菌や真菌(カビ)などが原因のものが多くみられます。代表的なものとして以下のようなものがあります。食物アレルギー、ノミアレルギー性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、膿皮症、疥癬(ヒゼンダニ)などです。もちろんこのような皮膚疾患がある場合は獣医師の指示に従ってケアを行ってください。

自宅でスキンケアを行うことも大切です。定期的なシャンプーや日々のブラッシングを行うこと、スキンケア向けのフードに切り替えるのも有効です。
また、適度な温度と湿度を保ち、愛犬愛猫が過ごす環境を快適に管理してあげましょう。
もしシャンプーの頻度やフードなどで迷った時にはわたしたち看護師や獣医師にご相談ください。
猫の泌尿器症候群(FUS)
猫の泌尿器症候群(FUS)は、尿が出にくい、血液が混じる、回数が多いなどの状態を総称して付けられた病名です。適切に管理しないと50~70%は再発すると言われており、オス猫に多い病気のひとつです。
FUSを起こす病気には、「膀胱炎」・「尿道炎」・「尿道栓」あるいは「尿道結石症」があります。メス猫には少なく、オス猫に多い理由は、尿道が膀胱からペニスに向かうところで急に細くなる部分があるためです
FUSの要因
尿の酸性度
ネコの尿は通常「酸性」ですが、食後の数時間や尿路に細菌感染ある場合にも「アルカリ性」に変化します。
尿が「アルカリ性」になると、酸性の状態であれば溶けているミネラルが結晶します。これらの結晶は次第に固まって結石となる可能性があり、ネコの尿路で見られる結石の9割はマグネシウム・アンモニア・リン酸塩(ストルバイト)というものです。
尿の量・濃度と排尿回数
飲水量が少なくなると、尿の量も少なくなりトイレに行く回数も減り、尿の濃度は高まります。トイレに行く回数が少なくなると尿が「アルカリ性」へ傾き、結石ができやすくなります。
結石と食事の影響
尿結石は十分な量のミネラルがなければ作られません。そのため、マグネシウムを多く含んだ食事だと結石が形成されやすくなります。逆にマグネシウムが少ない食事であれば結石は形成されにくく、FUSの発症を予防することができます。
初期症状
- 突然いつもと違う場所で排尿を始める。
- 何回も排尿姿勢はするが少量の排尿あるいは全く尿が出ない。
- 尿に血液が混じり、強いアンモニア臭がする。
- 落ち着かない、食欲がおちる、水をしきりに飲む。
- ペニスを気にして、しきりに舐める。…などの症状が見られます。
後期症状
排尿ができない状態が続いたり、感染が激しいと「尿毒症」に陥ります。
尿毒症の症状が見られます。嘔吐・沈うつ・脱水・尿臭のする息などです。
お腹を触ると固くゴムまりのように膨らんだ膀胱が感じられます。ネコは痛がり、触られるのを嫌がります。
末期症状
- 排尿が全くできなくなります。
- 痙攣を起こすことがあります。
- 昏睡状態に陥ります。
治療
尿道につまっているものを取り除く処置をおこないます。
細いカテーテル(プラスチックの管)を挿入して洗い流します。カテーテルを何日かつけたままにしておくこともあります。このとき、猫がカテーテルを抜かないようにカラーを付けます。
カテーテルの挿入や洗浄ができない場合は、超音波を使って結石を粉砕してからカテーテルを挿入します。
それでも取り除けないときは、開腹して手術をすることになります。
治療後について
ほとんどの猫は回復しますが、来院時の猫の状態によって治療後が左右されます。
回復後は、飼い主さんが獣医師の指示を守って注意深く観察してくださっていれば、寿命を全うさせることが可能です。
しかし、残念なことでが、来院時の猫の状態によっては、あらゆる治療の努力にもかかわらず、命を救うことができないこともあります。早期発見・早期治療が大切です。
予防と管理
- トイレはいつも清潔にし、安心して排尿できる場所を作りましょう。
- 水は新鮮で、自由にいつでも飲めるようにしておきましょう。
- 決められた食事(処方食)を、決められた時間に与えましょう。
- 症状が改善されても、指示された薬は確実に飲ませましょう。
- 環境の変化・環境温度・精神的動揺など、ストレスとなる要因を、できるだけ抑えるようにしましょう。
膀胱炎について
おしっこが少ししか出ない、頻尿になった、血尿がでる、などの症状で、動物病院にくるワンちゃんやネコちゃんが結構多くいます。いろいろな病気が考えられますが、そのなかで多いのが膀胱炎です。
膀胱は、尿道を通じて外界と接しています。そのため、尿道から細菌が侵入し、感染・炎症を起こしやすい臓器といえます。尿道の短いメスのほうがオスより膀胱炎になり易いようです。
細菌が侵入したからといって、必ず膀胱炎になるわけではありません。細菌感染に対する防御機能が、ちゃんと備わっています。尿によって洗い流したり、膀胱の内側の粘膜自体も感染に対する抵抗性を持っているのです。急性の膀胱炎のはほとんどは、細菌感染によるもの。膀胱炎の原因となる細菌は、たいてい糞便に由来する細菌で、尿道から上に行き感染するのです。しかし、排尿を我慢したり、神経障害や結石、腫瘍などによって排尿が妨げられたりすると、細菌の増殖を助けることになり、膀胱炎が起こりやすくなってしまうのです。このほかに結石、腫瘍、外傷などによっても膀胱炎になることが知られています。
膀胱炎の主な症状は、痛みを伴う排尿困難や頻尿。1回の排尿量が少なくなり、痛みのため鳴くことも…。残尿感があるので排尿姿勢を頻繁にとりますが、尿量は少しです。また、尿の色も健康なときは透明な黄色ですが、濃くなったり白く濁ったり、出血がある場合には血尿になります。以上のような症状がみられた、動物病院に直ちに連れて行ってあげましょう。
病院では、まず尿検査をします。尿の状態、結石がないか、細菌感染はないかなどを調べます。そのコの状態によっては、X線検査や超音波検査をおこなうこともあります。これにより、膀胱壁の肥厚や結石の有無、腫瘍の有無などが分ります。
検査により単純な細菌感染による膀胱炎であることがわかったなら、その原因菌に有効な抗生物質や抗菌剤を用いて治療します。薬の投薬は、最低でも2~3週間は必要です。飼い主さんの中には、症状が治ったらからといって自己判断で、薬をあげなくなったり、通院するのをやめてしまう方があります。こうした細菌感染は、きちんと治療し終えないと、再発したり、慢性化することがあるので、必ず獣医師の診断を受けてくださいね。
膀胱炎は放置したりすると病状が悪化したり、より重大な病気を起こすことがあります。ですから、排尿状態を日頃から観察し、異常があればすぐ病院に行ってください。
日頃から十分に新鮮な水を与え、排尿をさせることがとても大切です。また、不潔にすると細菌感染を起こしやすくなるので、常に清潔に保つことを心がけましょう。
狂犬病予防について
狂犬病の予防接種の時期(4月~)になりました。犬を飼っている人は狂犬病のワクチンを打つことが法律で義務付けられています。狂犬病とはどんな病気なのか。なぜ狂犬病のワクチンが義務付けられているのか。今回は狂犬病についてお話します。
狂犬病は狂犬病ウィルスの感染によって引き起こされる、代表的な人獣共通感染症です。ほとんどすべての哺乳動物が感染します。狂犬病ウィルスに感染して発病すると、致死的な脳炎を引き起こすため、ほぼ100%死亡します。潜伏期1~3ヵ月と長く、発病するまでの時期はさまざま。発病すると、まず強い不安感や精神的動揺に襲われます。そして次第に痙攣が起きます。水を飲み込むことができなくなり水を怖がるように見えます。さらに進行すると高熱、幻覚、錯乱、麻痺、運動失調がみられ、時には意味不明の叫びや、犬の遠吠えにもにた叫び声をあげることもあります。やがて全身痙攣が起き、ついには昏睡状態に。そして低血圧、不整脈、呼吸不全が起こり、やがて呼吸停止、心停止して死亡します。
狂犬病の予後はきわめて不良であり、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。現在までで発病し、回復した例は世界で3例といわれています。うち1例は、以前に狂犬病ワクチン接種を受けた研究者で、厳密な意味での回復例は米国での6歳男児とアルゼンチンでの45歳女性のみです。
狂犬病は人間が犬を飼い始めたころからあると思われ、最初に記録されたのは紀元前450年ごろのギリシャです。昔から世界中で恐れられている病気で、日本でも戦後までは発生がありました。1950年に狂犬病予防法が成立され、1957年には狂犬病の発生をゼロにすることができました。これには日本が島国であったこと、野生動物の間に狂犬病の流行がなかったこと、国民が狂犬病予防に協力的であったこと、などの理由が挙げられます。世界中の多くの国で発生し、日本のような狂犬病発生のない国は、いまだに数えるほどしかありません。WHOの統計によると、年間3万例以上発生しています。
狂犬病は、予防はできますが治すことができない恐ろしい病気です。狂犬病発生のない日本では、狂犬病発生をゼロに押さえることが最も望ましい予防策。狂犬病発生ゼロを続けるためには、狂犬病常在地からの狂犬病動物の侵入を防ぐことです。最近は様々な動物が輸入されています。検疫を受けていますが、検疫対象外動物や密輸入によって狂犬病感染動物が入ってくることも考えられます。侵入されても拡散しないように犬のワクチン接種率を高く維持することが必要です。
日本では半世紀近く発生がないため、狂犬病の恐ろしさが忘れ去られています。今後、日本で再発生が起きる可能性がないとは言いきれません。自分の飼っている犬が狂犬病にならないように、またそこから身近な人が感染しないようにするためにも、犬を飼っている人は狂犬病ワクチンを年に1回必ず打ちましょう。
猫のエイズ(FIV)
エイズ(AIDS:後天性免疫不全症候群)、人でよく知られている恐ろしい病気です。猫にも、ネコエイズといわれる病気が存在します。ご存じのように、ヒトのエイズは、HIV(ヒト免疫不全ウィルス)に感染することによっておこりますが、猫の世界にも、HIVとよく似たFIV(ネコ免疫不全ウィルス)というウイルスが存在します。
このFIVというウイルスは、猫から猫へとケンカによる咬傷や交尾により伝染します(人には伝染しないと言われています)。ネコエイズは、ワクチンもまだ日本では承認されていませんし、ウイルスを排除する治療法もありませんので、一度感染してしまうと一生ウイルスを保持し続けて、他の猫への感染源となってしまいます。地域性はありますが、野外の猫には、FIVは広く蔓延しているので、室内飼育の徹底などによって感染経路を絶つより方法はないでしょう。
あなたの猫が外出好きなコであれば、感染のリスクは高くなります。どうしても、完全室内飼育ができない場合でも、工夫をしてできるだけリスクを低くしてあげましょう。例えば、リードを付けての飼主さんとのお散歩で満足できるコもいます。避妊手術、去勢手術をすることで交尾による感染を防ぐこともできます。男の子ならば、去勢手術をすることでケンカの回数が減ることもあります。
ただ、このFIVは、名前こそ“ネコエイズウイルス”と言いますが、感染してもエイズ(免疫不全)の状態まで病状が進行してしまうことはあまりありません。発症するまでは、健康な猫と変わらない生活を送ることができます。免疫力の低下により、その他の疾病に感染しやすくなったり、治りにくくなったり、ひどい口内炎を患ったりといった症状がみられることがありますが、動物病院でその都度治療をうけながら、寿命を全うできる猫もいます。残念ながら最悪の場合は、発症し、免疫不全に陥り死に至ることもあります。
感染しているかどうかは、動物病院で血液の検査をすることでわかります。不運にもあなたの猫がFIVに感染してしまったとしても、悲観的にならず、より健康管理に気を配ってあげて、余生を楽に過ごさせてあげてください。
ただし、その猫が感染源になることは確かです。多頭飼育の場合、グルーミング程度では感染しませんが、ケンカや交尾をしないように、相性の悪い猫とは隔離するなどして気をつけてあげてください。また、その猫が外出すれば、外でケンカや交尾をすればさらにウイルスを広げてしまい感染猫を増やすことにつながります。飼主のモラルとして、避妊・去勢手術をおこない、外出させない工夫(前述)をしてあげましょう。
子猫を迎えたら~病気について~
すっかり暖かくなり、春めいてきました。年度もかわり新たな出会いが増えるシーズン。猫の出産時期でもあり、獣医師も子猫との出会いが多くなります。この時期、捨て猫やノラ猫の赤ちゃんを保護されることもあるかと思います。今回は子猫に見られる病気についてお話します。
子猫を迎えたら、顔をまず見てみましょう。くしゃみをしたり、鼻水や目やにが出ていませんか?ノラ猫など外で生まれた子猫には結構多く、ウィルスによる風邪が疑われます。ひどくなると、ゴハンが食べられなくなったりして衰弱してしまいます。放置しておくと慢性化してしまい、くしゃみや鼻水、目やに止まらなくなることもあります。根治させるためには、早めの治療必要です。
次に耳です。ひどく痒がったり、耳の中に黒い耳垢がたまっていませんか?疥癬という耳の中や皮膚に住みつくダニの寄生が疑われます。動物病院に行けば、顕微鏡による検査で発見することができ、適切な処置をすれば完治します。他の猫に感染しますし、人を刺すこともあるので、疑いがあるのなら早めの検査・治療することをお勧めします。
また、一見健康そうな子猫でも、便がゆるくなったり下痢をするコが多く見られます。子猫の下痢の主な理由としては、寄生虫および細菌などの感染によるものと、食事性の2つに分けられます。子猫は生体の防御機構や免疫反応が不充分なため、細菌や寄生虫の感染を受けたときに下痢を起こしやすいのです。その病原体は様々で、カンピロバクターやコクシジウム、回虫などがあります。また、子猫は離乳期にも下痢を起こしやすいので注意が必要です。母乳からそれ以外の食べ物を消化しなければならなくなるため、過食や消化しにくい食べ物の摂取など、わずかな負担によって消化不良を起こしやすいのです。成猫と違って、体力がない子猫の下痢は、生命の危険が伴うこともあります。子猫が下痢をするようでしたら、その便を持って動物病院へ行ってください。便を検査することにより原因を調べることができますし、すぐに対応した治療ができます。
健康に見える子猫でも病気を持っていることもあります。子猫を迎えたら、まず、動物病院で健康診断を受けることをお勧めします。
外耳道炎
夏、ジメジメとした暑い日が続きます。こうした高温多湿の環境になると起こりやすい疾患として、外耳炎があります。犬猫の外耳炎は、非常に多い疾患の一つです。病院の検診で偶然発見される軽度のものから、耳がただれ、強烈な痒みを伴い、夜も寝られないほど重度のものまで様々です。早期に発見し、治療すれば良い経過をたどりますが、放置しておくと慢性化し、治りづらくなります。
症状としては、耳を痒がる、頭を頻繁にふる、耳がくさい、黒や茶褐色の耳垢がついている、耳の中が赤い、首を傾けているなど、様々です。どれか一つでも当てはまるようなら、病院でチェックを受けることをおすすめします。
原因の中で、最も多いのが酵母様真菌(マラセチア菌)の繁殖によるもので、酵母性外耳道炎と呼ばれます。湿っぽい黒褐色の汚れと独特の発酵臭を伴います。このマラセチア菌は、もともと健康な犬猫の体に普通に常在する菌ですが、いろいろな要因で、異常に繁殖しすぎると病気を引き起こしてしまいます。マラセチア菌は、脂分を好み、高温多湿の環境で活発に増殖します。ですから、皮脂の分泌の盛んな品種(コッカーやシーズーなど)や垂れ耳の品種は通気性の悪くマラセチア菌が増殖しやすいといえます。この酵母性外耳道炎が悪化すると、そこに細菌が二次感染し、細菌性外耳道炎に移行してしまうことがあります。ここまでくると、耳道内は腫れて狭くなり、粘膜は爛れ、耳を触ると痛がります。また、強烈な腐敗臭を伴います。
治療は、抗菌剤の点耳が主体になります。早めに治療をしてあげると、ほとんどの場合がきちんと治癒しますが、体質や耳の形状は変わらないので、油断するとすぐ再発してしまいます。

垂れ耳の品種のコは
気をつけてあげましょうね
そのほかの原因としては、耳カイセン(耳ダニ)症といって、耳の中にダニの一種が寄生し、激しい痒みを引き起こすことがあります。耳の中には、黒っぽい乾燥した汚れがみられます。仔犬や子猫、ノラ猫などによくみられることがあります。この耳ダニは、他の犬や猫に感染しますので、注意が必要です。
それ以外には、耳道内の腫瘤や異物による閉塞、耳そうじのしすぎが原因になっていることもあります。
健康な犬や猫の耳垢は、ほとんどありません。定期的に耳垢の量や色などをチェックして耳垢が目立つようなら早めに動物病医院で治療をしてあげましょう。また、耳毛の多い子は、定期的に美容室か、動物病院で耳毛をぬいてもらい、通気性をよくしてあげましょう。ただ、先の固い綿棒などでのお掃除は、耳道内をかえって傷つけてしまうこともあるので気をつけてください。
お年寄りのワンちゃんがかかりやすい病気について
今回は、シニア犬がかかりやすい病気についてお話したいと思います。
ここ最近は、獣医学の向上や、栄養改善などにより、15歳を超える犬も珍しくなくなりました。犬は、だいたい8~9歳になると、若い頃のように、走り回ったりしなくなり、動きが鈍くなり、少しずつやせていって、食餌の量も、運動する量も減っていきます。また、視力や聴力も低下していきます。
高齢犬にみられやすい病気として主に腫瘍、白内障、心臓病、糖尿病などがあります。
腫瘍は、皮膚などにしこりができ、内臓にできた場合は、嘔吐や、血尿など様々な症状があります。時々、体を触ってしこりの有無をチェックしましょう。
白内障とは、瞳孔の奥の水晶体が老化で濁る病気です。眼が白く濁ってみえ、同時に視力が低下します。進行を遅らせることはできますが、完治は難しい病気です。犬の眼がみえにくいことを考えて、行動するようにしましょう。
心臓病といっていろいろな病気がありますが、そのなかでも特にかかりやすいのが、僧帽弁閉鎖不全と心筋症です。血液の循環をよくしたり、むくみを取る薬で治療します。と同時に、塩分控えめの食餌を与えます。その際、獣医師と相談してそのワンちゃんに適したドッグフードを選んであげて下さい。
糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが不足して、血糖値が高くなる病気です。症状としては、水を大量に飲んだり、しっかり食べてもやせてきます。十二分に運動させる規則正しい生活が最大の予防であり治療法です。肥満は大敵なので、気をつけましょう。

犬にも歳をとってくると、ぼけの症状が始まります。睡眠中に尿をもらしたり、外に出かけて帰れなくなったり、夜に起きて餌をほしがる、壁にぶつかるなど…。犬も家族の一員ですから、やさしく暖かい気持ちで愛犬に接してあげましょう。
愛犬のためにも、半年に一度は、動物病院に行って、検診を受けることをおすすめします。 一匹でも多くのワンちゃんが、少しでも長く健康に生活できるように、飼い主さんが気をつけてくれること、それが私たちの切なる願いです。
Photo:Yorikazu Inagaki・LinkStyle
犬の誤飲・誤食について
今回は、ワンちゃんの誤飲・誤食についてお話したいと思います。
誤飲・誤食とは文字通りワンちゃんが誤って飼い主さんの身の回りの物を飲み込んだり食べてしまうことです。誤飲・誤食による症状は、飲み込んだり食べたりするものによって様々です。
例えばオモチャの様な物や衣類、アクセサリーのような物の場合、胃や腸の閉塞を起こすことがあります。閉塞を起こすと盛んに嘔吐をするようになり、食欲や 元気が無くなり、放っておくと死に至ることもあります。閉塞が疑われるとき、または閉塞しそうな物を飲み込んだところを目撃した場合は、すぐに獣医師に相 談して下さい。飲み込んだことが曖昧な場合、レントゲン撮影などで確認します。飲み込んだ事が確認でき、比較的小さな物の場合、飲み込んで時間がそれほど たっていなければ、崔吐処置により吐き戻させることが可能な場合があります。吐き戻せない場合、以前は胃や腸を切開して取り出すのが当たり前でしたが、現 在は内視鏡を利用した摘出がかなりの場合で可能になっています。大きなボールのような物は今でもお腹を開かないとダメですが、靴下や小さな玩具のような物 は、ほとんどのケースで無切開で取り出せます。
笑えない話ですが、焼き鳥が付いたままの竹串、ストキング、ケロヨン人形、使い捨てひげそり、パンダのボールを飲み込んだコもいました。小さいコでは、ぬいぐるみの中綿を飲み込んだときに気管に詰まらせて死んでしまった症例もありました。全てが飼い主の不注意ばかりではありませんが、特に遊んでいる時に無理に取り上げようとすると、あわてて飲み込んでしまう事が多いようです。ワンちゃんが飲み込めそうな物で遊んでいるときにそれを取り上げる時は、いきなり取り上げるのではなく、何かに気をそらせた隙に取り上げるようにしましょう。また、間違って口にしたり飲み込んだりする可能性のあるものは、整理して手の届かない場所に置いておく工夫も必要です。

また、誤飲・誤食は前述のように物理的閉塞を起こす物だけでなく、クスリや農薬、毒性の植物や殺虫剤などのように体に吸収されることで影響を及ぼす場合もあります。こうした物を舐めたり飲んだりしたと思われる場合は、まずは獣医師にできるだけ早く連絡し「何をどのくらい誤食・誤飲して、現在はどんな状態か」を伝えてください。また、診察を受ける際には誤食・誤飲したと思われる現物とその成分表などを持っていくと診察に役立ちます。この場合の治療は様々ですが、嘔吐をさせたり、点滴で血液中の濃度を薄めたり、解毒剤を使ったり、吸着剤で吸収を抑えたり等が行われます。
なお、人間が食べても平気な物でもワンちゃんが食べると中毒を起こす物があります。ネギ類は赤血球を破壊し、チョコレートやコーヒーなどは神経症状や心不全などを引き起こします。これらの感受性は個体によりかなり差がありますので、少しだからと軽い気持ちで与えないようにしてください。
以上、いろいろと思いつくままに書いてきましたが、要は誤飲・誤食はさせないのが基本です。そしてもし、してしまった場合は上述のことを踏まえてできるだけ早く病院へお連れ下さい
Photo:平野 多聞i・LinkStyle
心臓病のお話
近年ペットの高齢化に伴い色々な病気と闘うワンちゃんネコちゃんが増えてきています。その中で心臓病はガンに続きペットの死因、そして罹患率共に上位にあげられます。心臓病は生まれ持つ場合と加齢によって起こる場合の2つのパターンがありますが、特に小型犬種の多い日本では加齢に伴う弁膜症の割合が高くなっています。今回は、その弁膜症についてお話しします。
最初に病気について軽く説明しようと思います。心臓には4つの部屋が存在し、その中で左側の上と下、右側の上と下にはそれぞれ逆流を防ぐ弁があり、それを介して血液が流れています。弁膜症というのはこの弁の閉まりが悪くなることで血液の流れが乱れる病態を言います。この時心臓はその責任感の強さから、乱れた血流を補うように今まで以上に頑張って動こうとします。ただそれは心臓自体を苦しめる結果となってしまうのです。その状態が長く続くと、心臓が悲鳴を上げ心不全の症状が出始めます。咳をしたり、運動を嫌がったりだとか、ひどいと肺や胸そしてお腹や足先など全身にお水が溜まってきてしまいます。肺に水がたまれば呼吸困難や失神を起こしたりすることもあります。そして多くのワンちゃんの顔つきが徐々に悲壮感漂うようになってきます。そうなると周りが見ても病的な感じとわかります。ペットは喋りませんが心臓病との闘いは心臓が悲鳴を上げる前から始まっているのです。
心臓病は徐々に進行していきますので、出来るだけ早い段階で心臓病だと解ってあげることがその後を大きく左右します。例えば最近咳をするだとか、あんまり散歩に行きたがらない、毛並みが悪く元気のない顔をしている、等が初期症状の場合が有りますので早めに獣医さんに診てもらった方がいいでしょう。聴診、超音波検査、レントゲン検査などで診断がつきます。最近では血液中のある種のホルモンを測定することでかなりの早期診断も可能になってきています。また安価な早期診断法として、定期的に診察を受け聴診してもらうことをおすすめします。症状がまだ出てない初期の段階で見つかることは結構多いものです。
心臓病と診断がついたら治療を始めます。治療のポイントは心臓の頑張りすぎを抑えることになりますので、そのような作用が期待できるお薬や食事を出来るだけ早くから始める事が大切です。但し、基本的に治療は一生継続する形になりますので、その覚悟は必要です。例えば途中でやめてしまうとひどくなることもあります。ただ可愛いワンちゃんが少しでも元気に長生きするためには周りのフォローが必要だと思います。
狂犬病のお話

犬を飼っていれば必ず知っていなくてはいけない病気の一つに、「狂犬病」という病気があります。
昔からある病気ですが、日本は世界中でも数少ない清浄国であり、過去50年以上にわたり日本国内での感染は認められていません。
ところが、2006年には二人の日本人が海外で感染し、帰国後発症したという事件がありました。
近隣諸国ではまだ狂犬病は根絶されておらず、いつ日本に入ってきてもおかしくないというのが現状であるため、改めて認識が必要な病気であるといえます。
狂犬病は、日本では犬の咬傷による感染や伝播が多かったので、狂犬病という名前が付けられていますが、人間を含め、他のほ乳類にも感染する「人獣共通感染症」です。感染した場合、暴露後免疫といって、万が一咬まれたら早急に治療用ワクチンを接種することで、発症前に狂犬病ウィルスを抑える治療法しかありません。
それでも間に合わなかったり咬まれた場所によっては、脳へウィルスが行ってしまい、発病することがあります。
そして、もし発症してしまうと、ほぼ100%死亡してしまう病気なのです。
このように、感染するとかなり恐ろしい病気である狂犬病の蔓延を防ぐため、日本では検疫や狂犬病予防法の制定を行いました。狂犬病予防法によって、最も感染源になりうる犬にワクチン接種を義務づけることで、日本は清浄国、常在国に比べて安心できる国となり、その発生を50年も防いでいます。
しかし、この安心感から過去の病気と思われつつもあります。
もし「もう大丈夫だろう」という気持ちから、狂犬病ワクチンを接種しないワンちゃんが増えてくると、海外から狂犬病が入ってきたときに一挙に国内に蔓延してしまう可能性があります。
現時点でも、日本の狂犬病ワクチンの接種率は安心できる数字はではないという調査結果もあり、みなさんには狂犬病の恐怖を再認識し、飼っているワンちゃんにしっかりワクチン接種を行ってほしいと思います。
また海外に行って、むやみに犬や野生動物に触らないようにしましょう。